院長紹介
一人でも多くの子が健康な心で社会に出れるように支援して
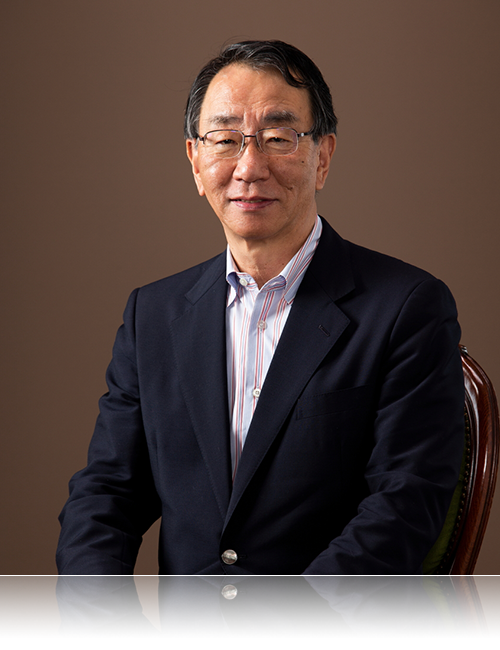
院長
大野 耕策 Kousaku Ohno
経歴
鳥取大学 昭和49年卒業
- 昭和49年5月
- 神奈川県立こども医療センター・ジュニアレジデント
- 昭和51年4月
- 鳥取大学医学部附属病院脳神経小児科(医員/助手)
- 昭和55年4月
- 九州大学医学部附属癌研究施設(医員/助手)
- 昭和56年4月
- 鳥取大学・助手/講師・医学部附属病院
- 昭和61年4月
- ノースカロライナ大学脳と発達研究所・客員研究員
- 昭和63年7月
- 鳥取大学・助教授・医学部・脳神経小児科部門
- 平成05年4月
- 鳥取大学・教授・医学部・生命科学科・神経生物学講座
- 平成13年7月
- 鳥取大学・教授・医学部・脳神経小児科分野
- 平成25年3月
- 鳥取大学・名誉教授
- 平成25年4月
- 独立行政法人労働者健康福祉機構 山陰労災病院・院長
所属学会
- 日本小児科学会 代議員
- 日本小児神経学会 名誉会員 前理事・前理事長
- 日本先天代謝異常学会 前理事・監事
専門医・認定医
- 日本小児科学会 専門医
- 日本小児神経学会 専門医
専門領域
- 遺伝性小児神経疾患
- 発達障害
令和元年6月3日に米子市西福原三丁目9-11に、おおの医院分院・こども発達クリニックを開業しました。
これまで勤務した大学病院や労災病院での日常診療の対象はほとんどが学校から紹介されてくる発達障害のお子さんでした。
平成26年4月から月1回、鳥取県いじめ不登校総合対策センターの「専門医による教育相談会」を担当させていただき、不登校の児童・生徒も多く見るようになりました。
こだわりの強い子、対人スキルの未熟な子、不注意な子、多動な子、衝動的な行動の多い子、かんしゃくをよく起こす子は、自己肯定感が下がりやすく、学習の凸凹が出やすくなります。自己肯定感が下がると暴言を吐いたり、反抗的な態度をとったりするようになります。
このような子どもたちへの対応の第1歩は、家庭や学校で自己肯定感を高めることができるような対応をしていくことです。
2つ目には不注意やワーキングメモリーが低下していると学習の定着が不良になって、すべての学習が苦手になりやすくなります。指示が入りやすい環境と指示の出し方の工夫をしていくことが大切です。
これらをしっかりした上で、不注意や多動衝動性がある場合やイライラが強く興奮しやすい場合などには薬物療法をすることもあります。
不登校の児童生徒も不登校のきっかけに自己肯定感の下がるエピソード(いじめ、先生からの否定、失敗体験など)があることが多く、家庭で自己肯定感を高くしていくアプローチが必須です。また不登校になっている子は、不安や気分の落ち込みなどの精神症状を合併していることが多く、そのような場合には薬物療法を行い、病弱学級(学校)での支援を考えていきます。
一人でも多くの子が健康な心で社会に出れるように支援して行きたいと考えています。
